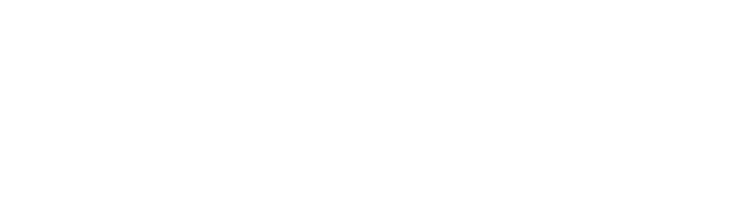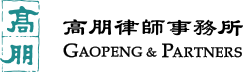方向性減資には株主全員の同意が必要ですか?
2025 03/06
事件の回顧
A、B、C、Dが共同出資してある貿易有限責任会社を設立した。同社の登録資本金は60万元で、そのうちA、Bは各10万元、C、Dは各20万元を出資し、A、B、C、Dが保有する株式の割合は16.7%、16.7%、33.3%、33.3%である。同社定款は、株主が出資比率に応じて議決権を行使し、株主会会議が登録資本を減らす決議を全株主の3分の2以上の議決権を代表する株主が通過しなければならないと規定している。その後、Aは方向性減資を通じて脱退しようとしたが、そのために株主4人は株主会を開き、A、C、Dの3人の株主の同意を得て、10万元減資し、株主Aは脱退し、株主B、C、Dの持株比率は同時に20%、40%、40%に変更する株主会決議を行った。株主Bは株主会決議に署名し、「減資決議に同意せず、違法減資に該当する」と明記し、その後裁判所に起訴し、前述の減資の株主決議が成立していないことを確認するよう求めた。
本件における株主決議が成立しないかどうかについては、2つの異なる見方がある。
1つの観点は、「会社法」第66条第3項と同社定款の規定に基づいて、株主が登録資本を減らす決議を行うには、3分の2以上の議決権を代表する株主が通過しなければならないと考えている。株主決議案が代表の3分の2以上の議決権を持つ株主によって可決されたため、株主決議案が成立した。
もう一つの観点では、株主は減資を志向し、株主の持ち株比率を変え、株主全員の一致同意を得なければならないと考えている。そのため、株主に関する決議は成立しない。
弁護士の分析
減資は2種類に分けられる:1つは非指向的減資であり、前年同期比減資とも呼ばれ、会社が株主の既存出資比率または持株比率に基づいて減資を行うこと、すなわち各株主の出資額または保有株式数はすべて同じ比率で減少することを指す。前年同期比の減資は株主間の持ち株比率を変えることはなく、会社設立時の株式分配状況を突破することもないことがわかる。もう1つは指向性減資であり、異なる比減資とも呼ばれ、各株主が減資過程で減少した出資または株式はその既存の持ち株比率ではなく、会社定款の特別規定または全株主の特別約束に基づいて調整され、一般的な場合は定向減資を通じて、個別株主が撤退を実現することを指す。このように、方向性減資は通常、株主間の持ち株比率を変え、会社設立時の株式分配状況を突破する。株式は株主が会社の権益を享受し、義務を負う基礎であるため、方向性減資後、会社設立時の発起人一致決議によって形成された株式比率の構造を変更し、会社の債務返済能力と資本信用の低下を招き、ひいては非減資株主にリスクをもたらす可能性がある。
司法実践の中で、「会社法」第66条第3項の株主は登録資本の決議を減らすことができ、「3分の2以上の議決権を代表する株主が通過しなければならない」という規定は、非指向性減資にのみ適用され、減資後の株主間の株式の分配をカバーしてはならないと考えている。同時に、「会社法」第224条第3項「会社が登録資本を減少させるには、株主の出資または保有株式の割合に応じて出資額または株式を減少させなければならず、法律に別途規定があり、有限責任会社の全株主が別途約束がある、または株式会社の章に別途規定がある場合を除く。」の規定に基づき、有限責任会社にとって、方向性減資は全株主または会社定款に別途約束がある場合を除き、全株主が一致して同意しなければならない。議決権の3分の2以上の株主が通過するだけで方向性減資決議を行うことができるため、実際には多数の決定形式で会社設立時に発起人の一致同意によって形成された株式比率の構造を変更し、実質的に未脱退株主が負うリスクを増加させ、ある程度未脱退株主の利益、特に会社の対外負債の場合に損害を与えた。
審理を経て、裁判所は本件の係争株主会決議が減資後の株式比率の再分配に関連していると判断し、Bの同意を得ない場合、各株主の株式比率の構造について合意に達していないとみなし、そのため係争株主会決議は成立しない。
A、B、C、Dが共同出資してある貿易有限責任会社を設立した。同社の登録資本金は60万元で、そのうちA、Bは各10万元、C、Dは各20万元を出資し、A、B、C、Dが保有する株式の割合は16.7%、16.7%、33.3%、33.3%である。同社定款は、株主が出資比率に応じて議決権を行使し、株主会会議が登録資本を減らす決議を全株主の3分の2以上の議決権を代表する株主が通過しなければならないと規定している。その後、Aは方向性減資を通じて脱退しようとしたが、そのために株主4人は株主会を開き、A、C、Dの3人の株主の同意を得て、10万元減資し、株主Aは脱退し、株主B、C、Dの持株比率は同時に20%、40%、40%に変更する株主会決議を行った。株主Bは株主会決議に署名し、「減資決議に同意せず、違法減資に該当する」と明記し、その後裁判所に起訴し、前述の減資の株主決議が成立していないことを確認するよう求めた。
本件における株主決議が成立しないかどうかについては、2つの異なる見方がある。
1つの観点は、「会社法」第66条第3項と同社定款の規定に基づいて、株主が登録資本を減らす決議を行うには、3分の2以上の議決権を代表する株主が通過しなければならないと考えている。株主決議案が代表の3分の2以上の議決権を持つ株主によって可決されたため、株主決議案が成立した。
もう一つの観点では、株主は減資を志向し、株主の持ち株比率を変え、株主全員の一致同意を得なければならないと考えている。そのため、株主に関する決議は成立しない。
弁護士の分析
減資は2種類に分けられる:1つは非指向的減資であり、前年同期比減資とも呼ばれ、会社が株主の既存出資比率または持株比率に基づいて減資を行うこと、すなわち各株主の出資額または保有株式数はすべて同じ比率で減少することを指す。前年同期比の減資は株主間の持ち株比率を変えることはなく、会社設立時の株式分配状況を突破することもないことがわかる。もう1つは指向性減資であり、異なる比減資とも呼ばれ、各株主が減資過程で減少した出資または株式はその既存の持ち株比率ではなく、会社定款の特別規定または全株主の特別約束に基づいて調整され、一般的な場合は定向減資を通じて、個別株主が撤退を実現することを指す。このように、方向性減資は通常、株主間の持ち株比率を変え、会社設立時の株式分配状況を突破する。株式は株主が会社の権益を享受し、義務を負う基礎であるため、方向性減資後、会社設立時の発起人一致決議によって形成された株式比率の構造を変更し、会社の債務返済能力と資本信用の低下を招き、ひいては非減資株主にリスクをもたらす可能性がある。
司法実践の中で、「会社法」第66条第3項の株主は登録資本の決議を減らすことができ、「3分の2以上の議決権を代表する株主が通過しなければならない」という規定は、非指向性減資にのみ適用され、減資後の株主間の株式の分配をカバーしてはならないと考えている。同時に、「会社法」第224条第3項「会社が登録資本を減少させるには、株主の出資または保有株式の割合に応じて出資額または株式を減少させなければならず、法律に別途規定があり、有限責任会社の全株主が別途約束がある、または株式会社の章に別途規定がある場合を除く。」の規定に基づき、有限責任会社にとって、方向性減資は全株主または会社定款に別途約束がある場合を除き、全株主が一致して同意しなければならない。議決権の3分の2以上の株主が通過するだけで方向性減資決議を行うことができるため、実際には多数の決定形式で会社設立時に発起人の一致同意によって形成された株式比率の構造を変更し、実質的に未脱退株主が負うリスクを増加させ、ある程度未脱退株主の利益、特に会社の対外負債の場合に損害を与えた。
審理を経て、裁判所は本件の係争株主会決議が減資後の株式比率の再分配に関連していると判断し、Bの同意を得ない場合、各株主の株式比率の構造について合意に達していないとみなし、そのため係争株主会決議は成立しない。