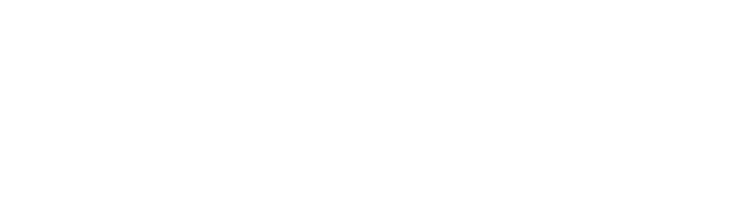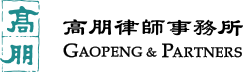AI創作に著作権はあるのか?
2025 03/11
事件の状況を回顧する.
張さんはあるAI生成ソフトを利用して、一連の指令情報を入力することで、春節をテーマにした画像を生成し、ネット上に公開した。その後、ネット上のあるブロガーのチョ氏がこの画像の署名透かしを削除したことが発覚し、その曲の作品の中で背景図として発表された。張さんは趙さんがAI生成画像の著作権を侵害しているとして、裁判所に訴訟を起こした。趙氏はAI画像はパソコンで生成されたものであり、張さん自身が描いたものではないので、著作権を持つべきではないと考えている。
弁護士の分析
実際、裁判所は著作権関連事件を判断するには、まず事件の文字、画像、動画などが法的な意味での「作品」を構成しているかどうかを確認する必要がある。実際には、以下の点から「作品」を構成するかどうかを認定します。
一、文学、芸術、科学分野に属する。例えばラジオ体操の動作は裁判所の判決で著作権を持たないと認定されたことがある。それは体を鍛えることを目的とした運動であり、動作を通じて思想感情を表現するのではなく、文学、芸術、科学の分野に属していないからだ。
二、独創性がある。作者は独立して完成し、個性的な表現を体現しており、既存の作品を盗作したり、編集したりしてはならない。
三、一定の形で表現できる。公衆が読んだり、鑑賞したり、複製したり、伝播することができます。
四、知力を払った成果に属する。作品は著者が知恵を入れて構想、構図、修正などを行った結果生まれたものである。例えば彫刻された石や木彫りで作品を構成し、天然に形成された怪石や樹木などは知的成果ではない。
AI創作が作品を構成するかどうかについては、実践の中で一概には言えない。もしクリエイターが何度も提示語を入力し、関連パラメータを調整し、内容を編集し、絶えず修正し、大量の知力の支払いによって得られた最終的な成果であれば、この成果はクリエイター個人の審美と個性化の調整修正を体現し、知力投入後に発生した独創性のある成果であれば、作品を構成し、著作権を持つと認定することができる。しかし、ビッグデータシステムから検索するだけでは、これまで他人が作った作品を直接提示したり、簡単に寄せ集めたりすることはできません。
現在、AIという新興分野では多くの法的問題が模索を待っている。注意しなければならないのは、AIが生成したコンテンツが他人の著作権保護された作品に基づいて二次創作を行った場合、使用前に相応の許可を得なければならず、そうでなければ権利侵害になる可能性があるということだ。
張さんはあるAI生成ソフトを利用して、一連の指令情報を入力することで、春節をテーマにした画像を生成し、ネット上に公開した。その後、ネット上のあるブロガーのチョ氏がこの画像の署名透かしを削除したことが発覚し、その曲の作品の中で背景図として発表された。張さんは趙さんがAI生成画像の著作権を侵害しているとして、裁判所に訴訟を起こした。趙氏はAI画像はパソコンで生成されたものであり、張さん自身が描いたものではないので、著作権を持つべきではないと考えている。
弁護士の分析
近年、人工知能科学技術は急速に発展し、それに伴う法律問題も次々と発生している。AI生産の成果が著作権を持っているかどうかを簡単に一概に判断するには、具体的なケースに基づいて、それぞれの研究判断を行う必要がある。
『著作権法』第3条は、本法でいう作品とは、文学、芸術、科学分野において独創性を持ち、一定の形式で表現できる知的成果を指すと規定している。
実際、裁判所は著作権関連事件を判断するには、まず事件の文字、画像、動画などが法的な意味での「作品」を構成しているかどうかを確認する必要がある。実際には、以下の点から「作品」を構成するかどうかを認定します。
一、文学、芸術、科学分野に属する。例えばラジオ体操の動作は裁判所の判決で著作権を持たないと認定されたことがある。それは体を鍛えることを目的とした運動であり、動作を通じて思想感情を表現するのではなく、文学、芸術、科学の分野に属していないからだ。
二、独創性がある。作者は独立して完成し、個性的な表現を体現しており、既存の作品を盗作したり、編集したりしてはならない。
三、一定の形で表現できる。公衆が読んだり、鑑賞したり、複製したり、伝播することができます。
四、知力を払った成果に属する。作品は著者が知恵を入れて構想、構図、修正などを行った結果生まれたものである。例えば彫刻された石や木彫りで作品を構成し、天然に形成された怪石や樹木などは知的成果ではない。
AI創作が作品を構成するかどうかについては、実践の中で一概には言えない。もしクリエイターが何度も提示語を入力し、関連パラメータを調整し、内容を編集し、絶えず修正し、大量の知力の支払いによって得られた最終的な成果であれば、この成果はクリエイター個人の審美と個性化の調整修正を体現し、知力投入後に発生した独創性のある成果であれば、作品を構成し、著作権を持つと認定することができる。しかし、ビッグデータシステムから検索するだけでは、これまで他人が作った作品を直接提示したり、簡単に寄せ集めたりすることはできません。
現在、AIという新興分野では多くの法的問題が模索を待っている。注意しなければならないのは、AIが生成したコンテンツが他人の著作権保護された作品に基づいて二次創作を行った場合、使用前に相応の許可を得なければならず、そうでなければ権利侵害になる可能性があるということだ。