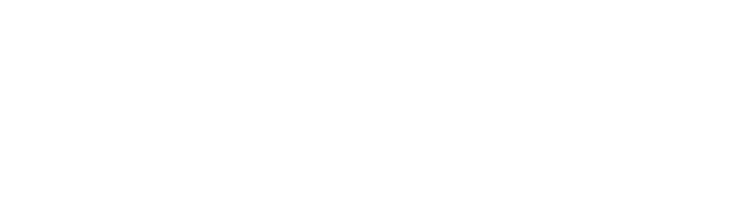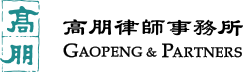ブルブル音で私憤を漏らすのは違法ですか?
2025 04/03
張三は2021年7月に甲会社を退職した。2021年9月から2022年1月までの間、張三氏は震えるプラットフォームで動画を投稿し続け、ネット上の注目を集め、甲社に怒りを漏らし、圧力をかけたいと考えている。動画は主に2つの部分に関連している:一部は張三と甲会社の労働争議に基づいて、その権利擁護、コミュニケーションの過程を公開すること、もう一部は甲社への暴露とコメントだ。甲社はこれにより名誉権侵害訴訟を提起し、張三に相応の法的責任を負わせるよう求めた。
裁判所は審理を経て、張三が民事責任を負うべきかどうかについて、双方の当事者の身分と言論の背景、影響範囲、過失の程度及び行為の目的、方式、結果などの要素を考慮して総合的に判断しなければならないと判断した。甲会社は営利法人として、他人に一定の事実根拠がある批判と質疑に対して相応の容認義務を負う。張三氏は自分の認知範囲内で事実を述べ、観点を表現し、世論監督の役割をある程度発揮することができ、社会公共利益の増進に役立つ。そのため、張三が動画で発表した発言については、状況に応じて処理しなければならない。
(1)客観的事実に基づく主観的な評論は、根拠がなく、明らかに不当ではなく、権利侵害を構成しない。
(2)交渉過程に基づいて自身の感覚と結びつけた結論に対して、「鹿を指して馬と為す」、「黒白を転倒する」、「神論理」などの言葉が皮肉で鋭い言い回しを用いているが、まだ許容範囲内であり、権利侵害を構成していない。
(3)個人の疑問を表明する態度に対して、具体的な侮辱や誹謗に関する内容が存在しない場合、権利侵害を構成しない。
(4)言論内容に対して観点表現と批判監督の範疇を超えた場合、甲会社に対する名誉侵害を構成し、以下を含む:
①証拠の支持や根拠が明らかに不足していない、あるいは明らかな誤解がある場合、
②事実の誇張、歪曲、偏在、断章、意味を取り、合理的な評論の限度を超えた場合
③甲会社の「人の血まんじゅうを食べる」、「貧乏」と「だます」、「クズ」、「詐欺師」、「恥知らず」などを形容し、いずれも貶め、侮辱の性質を持ち、用語は明らかに適切ではない。
最終的に裁判所は張三の一部の発言内容に甲会社に対する貶めと攻撃が存在すると認定し、すでに観点表現と批判監督の範疇を超え、明らかな主観的悪意があり、甲会社に対して社会評価の低下などの影響を与え、甲会社の名誉を損害し、権利侵害を構成し、権利侵害の責任を負わなければならない。そして、張三は甲会社に書面で謝罪し、甲会社の経済損失と権利維持コスト(弁護士費、公証費などを含む)を賠償するよう命じた。
近年台頭している微信、ドトーン、微博などの新型ソーシャルメディアプラットフォームは、公衆が個人的な意見を発表する重要な窓口となっている。しかし、プラットフォーム上での発言にも根拠があり、節があり、事実を捏造し、歪曲し、虚偽または侮辱、誹謗、貶める情報を流布すれば、他人の名誉権の侵害になる可能性があり、法的責任を負う必要がある。プラットフォームに掲載された発言が自分の名誉を損なっていることに気づいた場合は、最初に相手に侵害を停止し、法律的な方法で自分の合法的権益を守るように要求しなければならない。
裁判所は審理を経て、張三が民事責任を負うべきかどうかについて、双方の当事者の身分と言論の背景、影響範囲、過失の程度及び行為の目的、方式、結果などの要素を考慮して総合的に判断しなければならないと判断した。甲会社は営利法人として、他人に一定の事実根拠がある批判と質疑に対して相応の容認義務を負う。張三氏は自分の認知範囲内で事実を述べ、観点を表現し、世論監督の役割をある程度発揮することができ、社会公共利益の増進に役立つ。そのため、張三が動画で発表した発言については、状況に応じて処理しなければならない。
(1)客観的事実に基づく主観的な評論は、根拠がなく、明らかに不当ではなく、権利侵害を構成しない。
(2)交渉過程に基づいて自身の感覚と結びつけた結論に対して、「鹿を指して馬と為す」、「黒白を転倒する」、「神論理」などの言葉が皮肉で鋭い言い回しを用いているが、まだ許容範囲内であり、権利侵害を構成していない。
(3)個人の疑問を表明する態度に対して、具体的な侮辱や誹謗に関する内容が存在しない場合、権利侵害を構成しない。
(4)言論内容に対して観点表現と批判監督の範疇を超えた場合、甲会社に対する名誉侵害を構成し、以下を含む:
①証拠の支持や根拠が明らかに不足していない、あるいは明らかな誤解がある場合、
②事実の誇張、歪曲、偏在、断章、意味を取り、合理的な評論の限度を超えた場合
③甲会社の「人の血まんじゅうを食べる」、「貧乏」と「だます」、「クズ」、「詐欺師」、「恥知らず」などを形容し、いずれも貶め、侮辱の性質を持ち、用語は明らかに適切ではない。
最終的に裁判所は張三の一部の発言内容に甲会社に対する貶めと攻撃が存在すると認定し、すでに観点表現と批判監督の範疇を超え、明らかな主観的悪意があり、甲会社に対して社会評価の低下などの影響を与え、甲会社の名誉を損害し、権利侵害を構成し、権利侵害の責任を負わなければならない。そして、張三は甲会社に書面で謝罪し、甲会社の経済損失と権利維持コスト(弁護士費、公証費などを含む)を賠償するよう命じた。
近年台頭している微信、ドトーン、微博などの新型ソーシャルメディアプラットフォームは、公衆が個人的な意見を発表する重要な窓口となっている。しかし、プラットフォーム上での発言にも根拠があり、節があり、事実を捏造し、歪曲し、虚偽または侮辱、誹謗、貶める情報を流布すれば、他人の名誉権の侵害になる可能性があり、法的責任を負う必要がある。プラットフォームに掲載された発言が自分の名誉を損なっていることに気づいた場合は、最初に相手に侵害を停止し、法律的な方法で自分の合法的権益を守るように要求しなければならない。