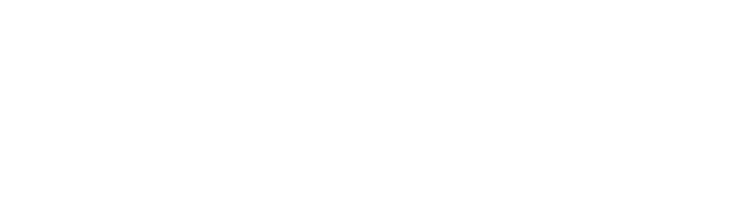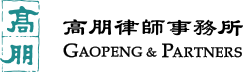「損をしたら私のものにして、お金を稼ぐのはみんなで分ける」の背後にはパートナーなのか、それともローンなのか。
事件の状況を回顧する.
チャン氏は果物屋を経営しようとしたが、資金が足りなかったため、親友の李氏を見つけ、李氏をパートナーに招待した。チャン氏は李氏に「店の経営は心配しなくてもいい。損をしたら私のものにし、稼いだらみんなのものにする」と約束した。李氏はこの安定したもうけを見て喜んで受け入れ、双方は『投資協力協定』を締結し、張氏が店舗運営を担当し、李氏が投資金10万元を支払い、毎月張氏が李氏に固定配当金2000元を支払うことを約束した。その後、チャン氏は一人で店を経営していた。しかし、1年後、しかし店の経営が悪いため、張氏は李氏に配当金を払い続けることができなかった。李氏は張氏の約束が履行されないのを見て、投資金を要求した。しかし、張氏は当初投資した金はすでに血を流していて、李氏もパートナーであり、一定の責任を負わなければならなかったと述べた。李氏は憤慨して裁判所に訴えた。
弁護士の分析
『民法典』第九百六十七条では、パートナー契約は2人以上のパートナーが共通の事業目的のために、利益を共有し、リスクを共有するための合意であると規定している。このことから、パートナーには共同投資、共同経営、収益の共有、リスクの共有といういくつかの特徴があり、パートナーが最終的に収益を得ることができるかどうかにも不確実性がある。双方のパートナーシップ契約において、一方が固定収益のみを享受し、経営に参加せず、リスクも負わないことを約束した場合、前述のパートナーシップ契約の特徴とは明らかに一致しない。
「『中華人民共和国国民法典』契約編通則の適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈」第15条は、人民法院が当事者間の権利・義務関係を認定するには、契約使用の名称にこだわるのではなく、契約約定の内容に基づいて行わなければならないと規定している。当事者が主張する権利義務関係と契約内容に基づいて認定された権利義務関係が一致しない場合、人民法院は締約の背景、取引目的、取引構造、履行行為及び当事者が架空取引の標的が存在するかどうかなどの事実を結合して当事者間の実際の民事法律関係を認定しなければならない。
『民法典』第六百六十七条によると、借入契約は借り手が貸手に借入し、満期になって借入金を返済し、利息を支払う契約である。貸借関係では、借り手が借入金を使用した後に収益を得たかどうかにかかわらず、借り手とは関係なく、双方の約束に従って満期に元金を返済して利息を支払うべきである。本件の一方が資金を提供し、固定的に収益を得る取引モデルは貸借の特徴に合致する。そのため、実際には裁判所はこのような関係を「パートナーと呼ばれ、実際には借り入れ」と認定し、最終的には借り入れ関係に基づいて認定し、固定配当金を借り入れによる利息に基づいて認定し、投資金の一方向を相手に返済し、一定額の利息を要求することが多い。