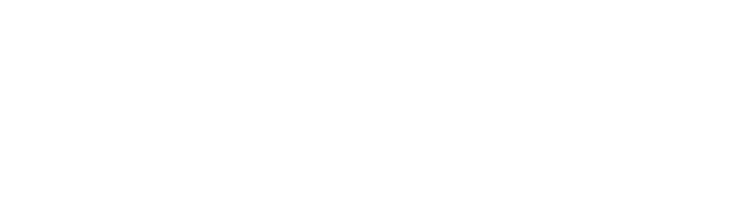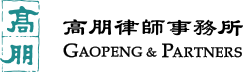労災を申告していない場合、使用者は人身損害賠償責任を負うか?
問題提起
2023年6月に張さんは仕事中に不注意で怪我をし、会社はその後休養を手配して給料を正常に支給したが、30日以内に労災認定を申請しなかった。張さんは将来的にも労働契約を更新したいと考えており、1年以内に労災認定を申請していない。2024年7月、張さんの労働契約が満期になり、会社は張さんに労働契約が満期になっても更新しないことを通知した。張さんは会社が自分が労災を起こしたことを顧みず、自分と労働契約を更新しないのは義理がないと思っている。そこで、張さんは会社を訴え、労災による損害賠償を求めた。では、張さんの訴えは裁判所の支持を得ることができるのだろうか。
弁護士の分析
公民の生命健康権は法に基づいて憲法と法律によって保護され、侵害された場合、賠償を主張する権利がある。『民法典』第1165条「行為者が過失により他人の民事権益を侵害して損害を与えた場合、権利侵害の責任を負わなければならない。」と『労災保険条例』の関連規定は、それぞれ人身損害と社会保険の角度から労災事故を規範化し、それにより労災事故に民事権利侵害賠償と社会保険賠償の二重の性質を持たせる。これに基づいて、労災が発生した労働者は法に基づいて2つの請求権を享有している:1つは労災保険関係に基づいて享有する労災保険待遇請求権であり、もう1つは人身損害に基づいて享有する民事侵害損害賠償請求権である。前述の2つの請求権は法的意義のある相互排斥性を持たないが、行使の面では適用の順序と期限に注意しなければならない。
労災が発生した後、労働者は優先的に労災認定を申請しなければならず、労災を認定すれば、法に基づいて労災保険待遇を受けることができる。「人身損害賠償事件の審理における法律の適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈」第3条第1項によると、「法により労災保険の統一的に計画された使用者に参加すべき労働者は、労災事故により人身損害を受け、労働者又はその近親者が使用者に民事賠償責任を請求するよう人民法院に提訴した場合、『労災保険条例』の規定に従って処理するよう通知する。」の規定により、労災が発生して人身損害を受けた場合、労働者又はその近親者は優先的に労災の関連規定に従って権利を主張し、直接民事事件に従って起訴するべきではない。なお、使用者が労災認定を申請する期間は30日であり、労働者又は家族が労災認定を申請する期間は1年である。この法定期限を超えると、社会保険行政機関は受理しなくなり、労働者は行政救済ルートを喪失し、すなわち労災保険待遇賠償を申請する権利を喪失した。
生命健康権は法律による優先保護の法的利益に属し、一定の優先性を持っているため、労働者は行政救済の道を失った後も、一般的な権利侵害に基づいて使用者に民事権利侵害損害賠償を主張する権利がある。賠償及び責任割合の負担については、原則として、裁判所は一般人身損害賠償民事事件として、『民法典』などの民事面の関連規定に基づいて責任の負担及び責任割合を判断する。しかし、司法の実践の中で、弱者を保護するために、使用者は労働者の労災に対して過失のない原則に基づいて一定の責任を負う。そのため、使用者の原因で労働者が労災保険の待遇を受けられない場合、多くの裁判所は使用者が従業員に権利侵害の責任を負わせることを支持し、医療費、介護費、誤工費、栄養費、鑑定費、障害賠償金などを含む「民法典」の規定に従って労働者に人身損害の賠償を行うことを支持している。また、民事侵害損害賠償請求権は民事訴訟時効3年の規定を適用し、時効期間は権利者が権利を知っているか、または権利が損害を受けたことと義務者を知っているべき日から計算する。
以上のことから、本件では、張氏は事故発生日から3年以内に民事侵害損害賠償を理由に、使用者に侵害損害賠償責任を負わせることができる。裁判所は、会社が人社部門に労災認定を申請すべきだと判断したが、同社は人社部門に労災認定を申請するのを怠り、張氏は法定期限を超え、行政救済の道を失ったため、同社に民事賠償責任を負うと判決した。