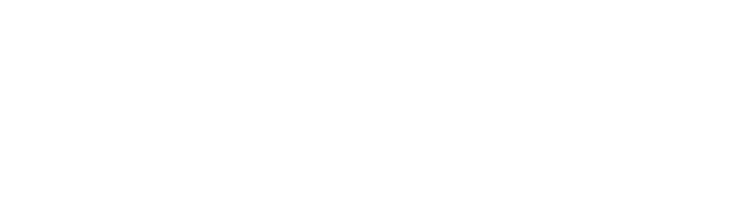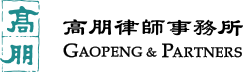税務弁護士は『税収徴収管理法(改正意見聴取稿)』を見る
2025 03/31
国家税務総局は財政部と共同で研究形成した『中華人民共和国税収徴収管理法(改正意見聴取稿)』(以下「『意見聴取稿』」と略称する)を3月28日から社会に公開して意見を求めた。「税収徴収管理法」は税務弁護士の毎日の必用として、筆者は自然に見ていられない。各条項の改正や削除は、筆者の手の中の税案に直接影響していると言える。この機会に、筆者は税務弁護士が最も注目しているいくつかの条項を選び、読者と一緒に『意見募集稿』を見て、適切に修正意見を提出した。【注:全文太字部分は「意見募集稿」に追加】
一、地域間の税収法執行の統一性と規範性を強化する
条項:『意見聴取稿』第5条第1項国務院税務主管部門は全国税収徴収管理業務を主管し、法に基づいて地域間税収法執行の統一性と規範性を強化しなければならない。各地の税務機関は国務院が規定した税収徴収管理範囲に従って徴収管理を行わなければならない。」
筆者の見解:
地域間の税収法執行の「統一性」を強調する。現在の税務処理過程では、異なる地域の税務機関が同じ行為に対して異なる処理方法をとる可能性があります。例えば、下流企業の「虚開を受け入れる行為」は、異なる地域間税務機関の処理方式が多様化している:善意の取得を認めたり、収入の転出を要求したり、付加価値税や延滞金を追納したり、定性的に「脱税」したり、公安に移送したりする。本条は法に基づいて法執行の統一性を強化することを強調し、これは異なる地域間税務機関が同類の税務事件に対して一貫性のある処理結果を提供することを要求する。この新たな表現は税務機関の法執行規範性の向上と納税者の権益保護に大いに役立つ。
二、情報共有メカニズムの実行
条目:『意見聴取稿』第6条第2項国務院税務主管部門は税収徴収管理業務の必要に応じて、国務院公安、金融管理、税関などの関係部門を通じて納税者の身分、口座、資金往来、輸出入など税収に関係する情報を検索することができ、関係部門は協力し、協力しなければならない。
筆者の見解:
ここ数年来、多くの部門が情報協力を強調する文章を送ってきたが、今回の徴収管理法改正はこの規定を法律面に上げて実行し、税務機関の徴収管理能力の強化に極めて役立つ。
三、税務機関の確定基準を明確にする
条項:『意見聴取稿』第13条第2項税務機関は税収違法行為を調査・処分し、事実がはっきりしており、証拠が十分であり、適用根拠が正しく、手順が合法であり、法に基づいて公平かつ公正に処理しなければならない。
筆者の見解:
本条は税務機関が税収違法行為を調査・処分するための確定基準を明確にした。これは『行政再議法』第68条、『行政訴訟法』第69条で確認された行政機関の具体的な行政行為が達成すべき基準と一致し、徴収管理法と関連法律の接続協調を強化した。
四、プラットフォーム経営者の責任強化
条項:『意見募集稿』第29条『中華人民共和国電子商取引法』に規定された電子商取引プラットフォーム経営者は、国務院税務主管部門が規定した期限と目録リストに従って、プラットフォーム内の経営者の身分情報と納税に関する情報を税務機関に報告しなければならない。その他のネットワーク取引プラットフォーム経営者は、前項の規定に従って、プラットフォーム内の経営者、従業員の身元情報及び納税に関する情報を税務機関に報告しなければならない。電子商取引プラットフォーム経営者及びその他のネットワーク取引プラットフォーム経営者は、国務院税務主管部門の規定に従って、プラットフォーム内の経営者、従業員の納税申告などの関連税金事項を処理しなければならない。」
筆者の見解:
2024年12月20日、国家税務総局は「インターネットプラットフォーム企業の税金関連情報の届出規定(意見聴取稿)」を公布し、プラットフォーム経営者はプラットフォーム内の経営者、従業員の納税申告を行うべきだと規定した。しかし、プラットフォーム内の経営者、従業員の数が多いことを考慮すると、プラットフォーム経営者は上述の主体に対して情報を報告する審査能力が限られており、情報の誤りによって税金の過少納付が発生する場合、その帰責問題は紛争を引き起こしやすいと考えている。そのため、本条の改正は未来の『インターネットプラットフォーム企業の税金関連情報の申告規定』と結びつけて、すべて税務機関、プラットフォーム経営者、プラットフォーム内経営者などの主体間の権利、義務及び責任の区分を明確にしなければならない。
五、非銀行支払機構の口座残高を強制執行範囲に組み入れる
条目:『意見聴取稿』第43本の税務機関は以下の強制措置を実施することができる:……(2)書面で非銀行支払機構に納税者を凍結する金額が納税金の支払口座残高に相当することを通知する、「……」「期限が切れても税金を納めていない場合、県以上の税務局(支局)の局長の許可を得て、税務機関は書面で銀行、その他の金融機関、非銀行支払機関にその凍結した預金、送金、非銀行支払機関が口座残高などの資産から税金を支払うよう通知したり、法に基づいて差し押さえられた商品、貨物またはその他の財産を競売または売却して、所得を競売または売却して税金を相殺したり、残りの部分は納税者に返却したりすることができる。
筆者の見解:
本条に新たに追加された強制措置は税務機関が税金未納を追徴する能力を増加させ、国家税金の適時入庫を保障するのに役立つ。実践操作には、税金滞納企業が他の債権債務紛争で裁判所の強制執行手続き中であり、裁判所が財産を執行した後、債権者に支払うべきだったが、税務機関は優先権を理由に執行された資金を先に税金を納付するよう要求した。筆者は、このような事件の中で税務機関は優先権を持っていないと考えている。同時に今回の改正では、税務機関がこの状況で優先権を持っていることは明らかにされておらず、この規定によってこのような紛争を効果的に抑制することができることを期待している。
六、租税滞納者の出国制限人員範囲を拡大する
条項:『意見聴取稿』第51条は、「税金未納の納税者又はその法定代表者、主要責任者、実際の支配者が出国する必要がある場合、出国前に税務機関に納税金、税金未納金を清算し、又は保証を提供しなければならない。税金、税金未納金を清算し、また保証を提供しない場合、税務機関は移民管理機構に出国を阻止するよう通知することができる」と規定している。
筆者の見解:
現行の租税徴収管理法と租税滞納者の出国阻止管理方法の規定によると、租税滞納者の出国制限の範囲は企業の法定代表者に限られている。今回の改訂稿では、主要責任者、実際の管理者が追加された。人員の範囲を拡大することは税金未納者に税金の完納を促すのに役立つが、企業の主要責任者と実際の支配者をどのように定義するかを明確に規定する法律規範はないため、実務では両者の身分定義が紛糾しやすい。両者の身元の具体的な測定基準をさらに明確にしないと、出国制限の手段ができた後、税金未納の効果を追徴する一方で、他の紛争を引き起こす可能性がある。
七、特別な状況下で出資者に税金を追徴することができることを明確にする
条項:『意見聴取稿』第56本の納税者の出資者は法人の独立地位と出資者の有限責任を濫用し、資金の引き出し、帳消しなどの手段を採用し、税務機関が納税者に未納、過少納付の税金または多還付の税金を追納できないようにし、情状が厳しい場合、税務機関は出資者に税金、税金の遅納金を追納しなければならない。
筆者の見解:
この新規条項は、新会社法第23条の法人人格否定制度に類似している。納税主体は会社(例えばパートナー企業)に限らないため、本条は「出資者」の概念を使用している。税案の発見と調査・処分に遅れがあるため、本条が最終的に新法に示されれば、将来的には多くの税務機関が出資者に企業の税金の納付を要求する可能性がある。税務執行法が法人の人格や出資者の有限責任を過度に突き破ることを防止するために、本条が適用される場合はさらに縮小することを提案する。
八、一部の状況を明確にした場合、多く申告した税金は返却しない
条目:『意見聴取稿』第59条第2項の規定によると、「省級以上の税務機関が国家の関係部門の申請または証拠に基づいて、納税者が融資、会社の上場、業績の増加、資格資格資格資格資格の取得などの目的のために税金を多く申告し納付した場合、税務機関は返却しない」。
筆者の見解:
実務には、納税者が融資、上場、業績の増加、またはある資格を取得した問題で対外的に領収書を発行した(下流は控除されず、コストも計上されていない)ため、発行者が付加価値税と企業所得税を多く納付した場合がある。この行為は『領収書管理方法』の規定に違反し、違法行為であるため、法律に保護されていない。本条はこの問題を明確にし、このような違法行為の発生を減らすのに役立つ。
九、未納又は過少納税の累計額が大きいことを明確にした場合、追徴期間は5年まで延長することができる
条項:『意見聴取稿』第59条第2項は、「納税者、源泉徴収義務者の計算ミスなどにより、税金を未納または過少納付した場合、税務機関は3年以内に追徴金、税金遅納金を追徴することができ、未納または過少納付の累計額が大きい場合、追徴期間は5年まで延長することができる」と規定している。
筆者の見解:
現行の「税収徴収管理法実施細則」第82条は、未納、過少納付の累計額が10万以上の場合、追徴期間を5年に延長すると規定している。本条の「累計額が大きい」という表現は、将来の実施細則の改訂に一定の細分化空間を与える。
十、税務検査時に納税者の非銀行支払口座を照会できることを明確にする
条項:『意見聴取稿』第62条の規定により、税務機関は以下の税務検査を行う権利がある:(9)県以上の税務局(支局)局長の許可を得て、全国統一形式の検査証明により、生産、経営に従事する納税者、源泉徴収義務者の非銀行支払機構における支払口座を検索する。税務機関は税収違法事件を調査する際、設置区の市、自治州以上の税務局(支局)の局長の許可を得て、事件の疑い者の非銀行支払機関の支払口座を照会することができる。税務機関が入手した資料を照会し、徴収管理以外の用途に使用してはならない。
筆者の見解:
経済の発展に伴い、既存の支払口座はすでに銀行などの金融機関の口座に限られておらず、本条は税務機関の税務検査範囲を非銀行支払機関の支払口座に拡大し、税務機関の徴収管理能力をさらに向上させた。
十一、納税者が立証責任を負うことを規定する
条項:『意見聴取稿』第66条第3項税務機関が収集した証拠に対して、当事者が明確に認可を表明した場合、当該証拠の証明効力を認定することができる、当事者が否定した場合は、十分に立証しなければならない。
筆者の見解:
本条の規定は行政法立証責任倒置の原則に違反し、『行政再議法』第46条、『行政訴訟法』第35条で確認された行政機関立証の原則と乖離している。上記の規定によると、再議手続きであれ訴訟手続きであれ、立証責任は行政機関の一方にある。本条は税務検査(査察)の段階で、当事者が税務機関が収集した証拠を否定する場合、十分に立証すべきであることをさらに明確にすべきだと筆者は考えている。しかし、税務行政の再議、訴訟の段階では、立証責任は税務機関に帰属しなければならない。
十二、新たに重大な税務事件の検査段階を追加しても関係者の出国を制限しなければならない
条項:『意見聴取稿』第68条の規定によると、税務機関は重大な税収違法事件の疑いがある場合、省、自治区、直轄市税務機関の許可を経て、移民管理機構に納税者及びその法定代表者、主要責任者、実際の制御者などの重要な事件関係者の出国を阻止するよう通知することができる。
筆者の見解:
『税務監査事件処理手順規定』第47条の規定に基づき、監査局は90日以内に結論を出すべきであるが、同時にこの規定は「事件が複雑で延期できる」という暗黙の了解をしており、これにより多くの税務事件が長引いている。また、税務機関が結論を出した後、納税者には再議と訴訟の権利があり、関連する具体的な行政行為は将来的に覆される可能性がある。そのため、事件の捜査中であれば関係者の出国を制限することは合理性を欠く。筆者は本条の削除を提案する。
十三、「脱税」と「脱税」を交換し、刑法及び司法解釈に規定された手段と統一する
条項:『意見聴取稿』第73条納税者は以下の手段を用いて虚偽の納税申告を行ったり、申告しなかったり、税金を納めなかったり、少なく納めたりしたのは、脱税である。納税者が脱税した場合、税務機関が未納または過少納付の税金、税金遅納金を追納し、未納または過少納付の税金の50%以上5倍以下の罰金を科す。犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する:
(一)帳簿、記帳証憑又はその他の税金関連資料を偽造、変造、移転、隠匿、無断で廃棄した場合電子証憑、電子領収書などの税金関連電子データまたは税金関連計算ソフトウェアパラメータ規則を改竄、偽造、不正に削除した場合、
(二)虚偽の税金計算根拠をでっち上げ、支出を水増しし、収入、財産を移転、隠匿し、または借用し、他人の名義を偽って収入を分解した場合
(3)虚偽の材料を提供するなどの手段を通じて、規則に違反して税収優遇を享受する場合、
(四)設立登記を行った納税者が課税行為が発生し、納税額が大きく申告しない場合
(五)法に基づいて設立登記をしていない納税者に課税行為が発生し、又は法に基づいて設立登記を行う必要がない納税者に課税行為が発生し、納税額が大きく、税務機関の通知を経て申告しない場合
(六)法律、行政法規に規定されたその他の脱税行為。
源泉徴収義務者は前項に記載された手段を採用し、源泉徴収済み、徴収済みの金を納付しない、または過少納付した税金、税金遅納金を税務機関が追納し、納付しない、または過少納付した税金の50%以上5倍以下の罰金を科す、犯罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。
納税者が税金を納付した後、本条に記載された手段を用いて輸出税金還付以外の税金還付金をだまし取った場合、本条第1項の規定に従って処理、処罰する。
筆者の見解:
本条は「課税行為が発生し、納税額が大きく申告しない」という構成脱税を明確にしており、将来的にはそれに合わせて改正された「徴収管理法実施細則」は「額が大きい」と規定しなければならない。同時に、本条は現行の「徴収管理法」第63条と64条第2項を合併し、2024年3月20日に実施された2高の「危害税収徴収管理刑事事件の取り扱いに関する法律のいくつかの問題の解釈」(法釈〔2024〕4号)第1条に接続し、「申告しない」部分の状況を「脱税」に上昇させて定性的にする。また、脱税手段の中で第5項の状況ははっきりと表現されず、曖昧さを引き起こしやすいので、もう少し考えて表現する必要がある。
十四、「その他申告しない」場合の法的結果を明確にする
条項:『意見聴取稿』第74条納税者、源泉徴収義務者が本法第73条以外の規定通りに申告していないことにより未納または過少納税の状況が生じた場合、税務機関が未納または過少納付の税金、税金遅納金を追納する。情状が重い場合は、未納または過少納付の税金の50%以下の罰金を科すことができる。情状が深刻な場合、未納または過少納付の税金の50%以上1倍以下の罰金を科す。
筆者の見解:
『意見聴取稿』七十三条には、「設立登記を行った納税者が課税行為を行い、納税額が大きく申告しない構成脱税」及び「登記を設立していない納税者は、納税額が大きく、申告拒否を通知した構成脱税」が規定されている。しかし、実際には例外があるため、本条は脱税ではないが、小倍数の罰金を科すことができるようにするためのポケットを設置した。
十五、違法行為があっても税金の未納又は過少納付をもたらしていないことを明確にした場合、小額処罰すべき
条項:『意見聴取稿』第75本の納税者、源泉徴収義務者が虚偽の税金計算根拠をでっち上げたが、税金の未納または過少納付をもたらしていない場合、税務機関は期限付きで改正するよう命じ、5万元以下の罰金を科す。
筆者の見解:
本条には「未納または過少納付をもたらしていない」という前提条件が追加され、この表現は第73条と第75条の2つの条文の境界と適用をより明確にした。
十六、新たに「行政虚開」の処理方式を追加する
条項:『意見聴取稿』第83条他人のため、自分のため、他人に自分のため、他人に実際の経営業務状況と一致しない領収書を発行させる場合、虚発票行為を構成し、税務機関が違法所得を没収し、50万元以下の罰金を科すことができる、領収書を偽造した金額が巨大な場合、50万元以上500万元以下の罰金を科す。犯罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。
納税者が領収書を偽造して不法に援助を提供した場合、税務機関はその違法所得を没収する以外に、5万元以下の罰金を科すことができる。
筆者の見解:
本条は初めて「行政虚開」を明確に規定した。しかし、本条の表現はさらに明確にしなければならず、「納税者は虚開行為をしているが、行政虚開だけを構成し、司法機関に移送して刑事責任を追及する必要がない場合、税務機関は不法所得を没収して罰金を科すことができる」ことを明確にしなければならない。
十七、他人の税収違法行為の実施に明確に協力した場合、処罰を受けるべき
条項:『意見聴取稿』第84本は納税者、源泉徴収義務者に銀行口座、領収書、証明書及びその他の便宜を不法に提供し、或いは納税者を教唆、誘導、援助し、源泉徴収義務者が税収違法行為を実施し、未納、過少納税又は国家輸出還付金をだまし取った場合、税務機関はその違法所得を没収する以外に、未納、過少納付又はだまし取った税金の1倍以下の罰金を処することができる。
筆者の見解:
本条では、他人の脱税に協力するには行政責任を問われるべきだと初めて規定している。しかし、本条の「その他の便宜」は実務における拡大解釈をもたらしやすく、紛争を引き起こし、行政相対人の権益を損なう可能性がある。したがって、本条の「その他の便宜」に対して明確な順方向列挙を行うことを提案する。
十八、納税前置手続を、再議前から、訴訟前に変更する
条目:『意見聴取稿』第101条第1項は納税者、源泉徴収義務者、納税保証人と税務機関との納税上の紛争が発生した場合、法に基づいて行政再議を申請することができる、行政再議決定に不服がある場合は、まず税務機関の決定に基づいて税金及び税金の遅納金を納付または解納するか、または相応の保証を提供しなければならず、それから法に基づいて人民法院に起訴することができ、人民法院は税務機関が発行した納税証明書または保証証明書に基づいて受理しなければならない。
筆者の見解:
実務の中で、現行の「徴収管理法」第88条、「税務行政再議規則」第33条の規定に基づき、納税者は税金を先に納付したり、納税保証を提供したりすることができないため、救済ルートを失った。本条は「納税前置」を再議後、訴訟前に置くことで、納税者の救済ルートを広げることができる。しかし、納税者の合法的権益をよりよく保護し、その救済ルートを確立するためには、正式に「納税前置」手続きを取り消すべきだと筆者は考えている。
19、税務サービス機構に対する監督管理を強化する
条項:『意見聴取稿』第百二条第二項国は税金関連専門サービス機構が法に基づいて税務代理業務を展開することを奨励し、税務機関は税金関連専門サービス機構と個人が税金関連専門サービスに従事する監督管理を強化しなければならない。
筆者の見解:
税務機関は「個人が税金関連専門サービスに従事するための監督管理」の内容を強化するのは広すぎて、操作性がない。筆者は現行の法律の規定に基づいて、税務機関は関連法律に限られた範囲内で税金関連専門サービス機構を監督管理すればよいと考えている。
小結
今回の改正は税務執行のレベルを強化し、納税者のコンプライアンスを高めるのに大いに役立つ。上記の筆者が注目している条項のほか、今回の「意見聴取稿」にはいくつかの改正が行われ、現行の税収徴収管理法より16条、4条削除、69条が新たに追加された。読者が今回の「意見聴取稿」に注目して検討することを歓迎し、読者の友人が4月27日までに関係機関に有益な改正提案を提出し、我が国の税収法治建設のプロセスを共同で推進することを提案することを提案する。
一、地域間の税収法執行の統一性と規範性を強化する
条項:『意見聴取稿』第5条第1項国務院税務主管部門は全国税収徴収管理業務を主管し、法に基づいて地域間税収法執行の統一性と規範性を強化しなければならない。各地の税務機関は国務院が規定した税収徴収管理範囲に従って徴収管理を行わなければならない。」
筆者の見解:
地域間の税収法執行の「統一性」を強調する。現在の税務処理過程では、異なる地域の税務機関が同じ行為に対して異なる処理方法をとる可能性があります。例えば、下流企業の「虚開を受け入れる行為」は、異なる地域間税務機関の処理方式が多様化している:善意の取得を認めたり、収入の転出を要求したり、付加価値税や延滞金を追納したり、定性的に「脱税」したり、公安に移送したりする。本条は法に基づいて法執行の統一性を強化することを強調し、これは異なる地域間税務機関が同類の税務事件に対して一貫性のある処理結果を提供することを要求する。この新たな表現は税務機関の法執行規範性の向上と納税者の権益保護に大いに役立つ。
二、情報共有メカニズムの実行
条目:『意見聴取稿』第6条第2項国務院税務主管部門は税収徴収管理業務の必要に応じて、国務院公安、金融管理、税関などの関係部門を通じて納税者の身分、口座、資金往来、輸出入など税収に関係する情報を検索することができ、関係部門は協力し、協力しなければならない。
筆者の見解:
ここ数年来、多くの部門が情報協力を強調する文章を送ってきたが、今回の徴収管理法改正はこの規定を法律面に上げて実行し、税務機関の徴収管理能力の強化に極めて役立つ。
三、税務機関の確定基準を明確にする
条項:『意見聴取稿』第13条第2項税務機関は税収違法行為を調査・処分し、事実がはっきりしており、証拠が十分であり、適用根拠が正しく、手順が合法であり、法に基づいて公平かつ公正に処理しなければならない。
筆者の見解:
本条は税務機関が税収違法行為を調査・処分するための確定基準を明確にした。これは『行政再議法』第68条、『行政訴訟法』第69条で確認された行政機関の具体的な行政行為が達成すべき基準と一致し、徴収管理法と関連法律の接続協調を強化した。
四、プラットフォーム経営者の責任強化
条項:『意見募集稿』第29条『中華人民共和国電子商取引法』に規定された電子商取引プラットフォーム経営者は、国務院税務主管部門が規定した期限と目録リストに従って、プラットフォーム内の経営者の身分情報と納税に関する情報を税務機関に報告しなければならない。その他のネットワーク取引プラットフォーム経営者は、前項の規定に従って、プラットフォーム内の経営者、従業員の身元情報及び納税に関する情報を税務機関に報告しなければならない。電子商取引プラットフォーム経営者及びその他のネットワーク取引プラットフォーム経営者は、国務院税務主管部門の規定に従って、プラットフォーム内の経営者、従業員の納税申告などの関連税金事項を処理しなければならない。」
筆者の見解:
2024年12月20日、国家税務総局は「インターネットプラットフォーム企業の税金関連情報の届出規定(意見聴取稿)」を公布し、プラットフォーム経営者はプラットフォーム内の経営者、従業員の納税申告を行うべきだと規定した。しかし、プラットフォーム内の経営者、従業員の数が多いことを考慮すると、プラットフォーム経営者は上述の主体に対して情報を報告する審査能力が限られており、情報の誤りによって税金の過少納付が発生する場合、その帰責問題は紛争を引き起こしやすいと考えている。そのため、本条の改正は未来の『インターネットプラットフォーム企業の税金関連情報の申告規定』と結びつけて、すべて税務機関、プラットフォーム経営者、プラットフォーム内経営者などの主体間の権利、義務及び責任の区分を明確にしなければならない。
五、非銀行支払機構の口座残高を強制執行範囲に組み入れる
条目:『意見聴取稿』第43本の税務機関は以下の強制措置を実施することができる:……(2)書面で非銀行支払機構に納税者を凍結する金額が納税金の支払口座残高に相当することを通知する、「……」「期限が切れても税金を納めていない場合、県以上の税務局(支局)の局長の許可を得て、税務機関は書面で銀行、その他の金融機関、非銀行支払機関にその凍結した預金、送金、非銀行支払機関が口座残高などの資産から税金を支払うよう通知したり、法に基づいて差し押さえられた商品、貨物またはその他の財産を競売または売却して、所得を競売または売却して税金を相殺したり、残りの部分は納税者に返却したりすることができる。
筆者の見解:
本条に新たに追加された強制措置は税務機関が税金未納を追徴する能力を増加させ、国家税金の適時入庫を保障するのに役立つ。実践操作には、税金滞納企業が他の債権債務紛争で裁判所の強制執行手続き中であり、裁判所が財産を執行した後、債権者に支払うべきだったが、税務機関は優先権を理由に執行された資金を先に税金を納付するよう要求した。筆者は、このような事件の中で税務機関は優先権を持っていないと考えている。同時に今回の改正では、税務機関がこの状況で優先権を持っていることは明らかにされておらず、この規定によってこのような紛争を効果的に抑制することができることを期待している。
六、租税滞納者の出国制限人員範囲を拡大する
条項:『意見聴取稿』第51条は、「税金未納の納税者又はその法定代表者、主要責任者、実際の支配者が出国する必要がある場合、出国前に税務機関に納税金、税金未納金を清算し、又は保証を提供しなければならない。税金、税金未納金を清算し、また保証を提供しない場合、税務機関は移民管理機構に出国を阻止するよう通知することができる」と規定している。
筆者の見解:
現行の租税徴収管理法と租税滞納者の出国阻止管理方法の規定によると、租税滞納者の出国制限の範囲は企業の法定代表者に限られている。今回の改訂稿では、主要責任者、実際の管理者が追加された。人員の範囲を拡大することは税金未納者に税金の完納を促すのに役立つが、企業の主要責任者と実際の支配者をどのように定義するかを明確に規定する法律規範はないため、実務では両者の身分定義が紛糾しやすい。両者の身元の具体的な測定基準をさらに明確にしないと、出国制限の手段ができた後、税金未納の効果を追徴する一方で、他の紛争を引き起こす可能性がある。
七、特別な状況下で出資者に税金を追徴することができることを明確にする
条項:『意見聴取稿』第56本の納税者の出資者は法人の独立地位と出資者の有限責任を濫用し、資金の引き出し、帳消しなどの手段を採用し、税務機関が納税者に未納、過少納付の税金または多還付の税金を追納できないようにし、情状が厳しい場合、税務機関は出資者に税金、税金の遅納金を追納しなければならない。
筆者の見解:
この新規条項は、新会社法第23条の法人人格否定制度に類似している。納税主体は会社(例えばパートナー企業)に限らないため、本条は「出資者」の概念を使用している。税案の発見と調査・処分に遅れがあるため、本条が最終的に新法に示されれば、将来的には多くの税務機関が出資者に企業の税金の納付を要求する可能性がある。税務執行法が法人の人格や出資者の有限責任を過度に突き破ることを防止するために、本条が適用される場合はさらに縮小することを提案する。
八、一部の状況を明確にした場合、多く申告した税金は返却しない
条目:『意見聴取稿』第59条第2項の規定によると、「省級以上の税務機関が国家の関係部門の申請または証拠に基づいて、納税者が融資、会社の上場、業績の増加、資格資格資格資格資格の取得などの目的のために税金を多く申告し納付した場合、税務機関は返却しない」。
筆者の見解:
実務には、納税者が融資、上場、業績の増加、またはある資格を取得した問題で対外的に領収書を発行した(下流は控除されず、コストも計上されていない)ため、発行者が付加価値税と企業所得税を多く納付した場合がある。この行為は『領収書管理方法』の規定に違反し、違法行為であるため、法律に保護されていない。本条はこの問題を明確にし、このような違法行為の発生を減らすのに役立つ。
九、未納又は過少納税の累計額が大きいことを明確にした場合、追徴期間は5年まで延長することができる
条項:『意見聴取稿』第59条第2項は、「納税者、源泉徴収義務者の計算ミスなどにより、税金を未納または過少納付した場合、税務機関は3年以内に追徴金、税金遅納金を追徴することができ、未納または過少納付の累計額が大きい場合、追徴期間は5年まで延長することができる」と規定している。
筆者の見解:
現行の「税収徴収管理法実施細則」第82条は、未納、過少納付の累計額が10万以上の場合、追徴期間を5年に延長すると規定している。本条の「累計額が大きい」という表現は、将来の実施細則の改訂に一定の細分化空間を与える。
十、税務検査時に納税者の非銀行支払口座を照会できることを明確にする
条項:『意見聴取稿』第62条の規定により、税務機関は以下の税務検査を行う権利がある:(9)県以上の税務局(支局)局長の許可を得て、全国統一形式の検査証明により、生産、経営に従事する納税者、源泉徴収義務者の非銀行支払機構における支払口座を検索する。税務機関は税収違法事件を調査する際、設置区の市、自治州以上の税務局(支局)の局長の許可を得て、事件の疑い者の非銀行支払機関の支払口座を照会することができる。税務機関が入手した資料を照会し、徴収管理以外の用途に使用してはならない。
筆者の見解:
経済の発展に伴い、既存の支払口座はすでに銀行などの金融機関の口座に限られておらず、本条は税務機関の税務検査範囲を非銀行支払機関の支払口座に拡大し、税務機関の徴収管理能力をさらに向上させた。
十一、納税者が立証責任を負うことを規定する
条項:『意見聴取稿』第66条第3項税務機関が収集した証拠に対して、当事者が明確に認可を表明した場合、当該証拠の証明効力を認定することができる、当事者が否定した場合は、十分に立証しなければならない。
筆者の見解:
本条の規定は行政法立証責任倒置の原則に違反し、『行政再議法』第46条、『行政訴訟法』第35条で確認された行政機関立証の原則と乖離している。上記の規定によると、再議手続きであれ訴訟手続きであれ、立証責任は行政機関の一方にある。本条は税務検査(査察)の段階で、当事者が税務機関が収集した証拠を否定する場合、十分に立証すべきであることをさらに明確にすべきだと筆者は考えている。しかし、税務行政の再議、訴訟の段階では、立証責任は税務機関に帰属しなければならない。
十二、新たに重大な税務事件の検査段階を追加しても関係者の出国を制限しなければならない
条項:『意見聴取稿』第68条の規定によると、税務機関は重大な税収違法事件の疑いがある場合、省、自治区、直轄市税務機関の許可を経て、移民管理機構に納税者及びその法定代表者、主要責任者、実際の制御者などの重要な事件関係者の出国を阻止するよう通知することができる。
筆者の見解:
『税務監査事件処理手順規定』第47条の規定に基づき、監査局は90日以内に結論を出すべきであるが、同時にこの規定は「事件が複雑で延期できる」という暗黙の了解をしており、これにより多くの税務事件が長引いている。また、税務機関が結論を出した後、納税者には再議と訴訟の権利があり、関連する具体的な行政行為は将来的に覆される可能性がある。そのため、事件の捜査中であれば関係者の出国を制限することは合理性を欠く。筆者は本条の削除を提案する。
十三、「脱税」と「脱税」を交換し、刑法及び司法解釈に規定された手段と統一する
条項:『意見聴取稿』第73条納税者は以下の手段を用いて虚偽の納税申告を行ったり、申告しなかったり、税金を納めなかったり、少なく納めたりしたのは、脱税である。納税者が脱税した場合、税務機関が未納または過少納付の税金、税金遅納金を追納し、未納または過少納付の税金の50%以上5倍以下の罰金を科す。犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する:
(一)帳簿、記帳証憑又はその他の税金関連資料を偽造、変造、移転、隠匿、無断で廃棄した場合電子証憑、電子領収書などの税金関連電子データまたは税金関連計算ソフトウェアパラメータ規則を改竄、偽造、不正に削除した場合、
(二)虚偽の税金計算根拠をでっち上げ、支出を水増しし、収入、財産を移転、隠匿し、または借用し、他人の名義を偽って収入を分解した場合
(3)虚偽の材料を提供するなどの手段を通じて、規則に違反して税収優遇を享受する場合、
(四)設立登記を行った納税者が課税行為が発生し、納税額が大きく申告しない場合
(五)法に基づいて設立登記をしていない納税者に課税行為が発生し、又は法に基づいて設立登記を行う必要がない納税者に課税行為が発生し、納税額が大きく、税務機関の通知を経て申告しない場合
(六)法律、行政法規に規定されたその他の脱税行為。
源泉徴収義務者は前項に記載された手段を採用し、源泉徴収済み、徴収済みの金を納付しない、または過少納付した税金、税金遅納金を税務機関が追納し、納付しない、または過少納付した税金の50%以上5倍以下の罰金を科す、犯罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。
納税者が税金を納付した後、本条に記載された手段を用いて輸出税金還付以外の税金還付金をだまし取った場合、本条第1項の規定に従って処理、処罰する。
筆者の見解:
本条は「課税行為が発生し、納税額が大きく申告しない」という構成脱税を明確にしており、将来的にはそれに合わせて改正された「徴収管理法実施細則」は「額が大きい」と規定しなければならない。同時に、本条は現行の「徴収管理法」第63条と64条第2項を合併し、2024年3月20日に実施された2高の「危害税収徴収管理刑事事件の取り扱いに関する法律のいくつかの問題の解釈」(法釈〔2024〕4号)第1条に接続し、「申告しない」部分の状況を「脱税」に上昇させて定性的にする。また、脱税手段の中で第5項の状況ははっきりと表現されず、曖昧さを引き起こしやすいので、もう少し考えて表現する必要がある。
十四、「その他申告しない」場合の法的結果を明確にする
条項:『意見聴取稿』第74条納税者、源泉徴収義務者が本法第73条以外の規定通りに申告していないことにより未納または過少納税の状況が生じた場合、税務機関が未納または過少納付の税金、税金遅納金を追納する。情状が重い場合は、未納または過少納付の税金の50%以下の罰金を科すことができる。情状が深刻な場合、未納または過少納付の税金の50%以上1倍以下の罰金を科す。
筆者の見解:
『意見聴取稿』七十三条には、「設立登記を行った納税者が課税行為を行い、納税額が大きく申告しない構成脱税」及び「登記を設立していない納税者は、納税額が大きく、申告拒否を通知した構成脱税」が規定されている。しかし、実際には例外があるため、本条は脱税ではないが、小倍数の罰金を科すことができるようにするためのポケットを設置した。
十五、違法行為があっても税金の未納又は過少納付をもたらしていないことを明確にした場合、小額処罰すべき
条項:『意見聴取稿』第75本の納税者、源泉徴収義務者が虚偽の税金計算根拠をでっち上げたが、税金の未納または過少納付をもたらしていない場合、税務機関は期限付きで改正するよう命じ、5万元以下の罰金を科す。
筆者の見解:
本条には「未納または過少納付をもたらしていない」という前提条件が追加され、この表現は第73条と第75条の2つの条文の境界と適用をより明確にした。
十六、新たに「行政虚開」の処理方式を追加する
条項:『意見聴取稿』第83条他人のため、自分のため、他人に自分のため、他人に実際の経営業務状況と一致しない領収書を発行させる場合、虚発票行為を構成し、税務機関が違法所得を没収し、50万元以下の罰金を科すことができる、領収書を偽造した金額が巨大な場合、50万元以上500万元以下の罰金を科す。犯罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。
納税者が領収書を偽造して不法に援助を提供した場合、税務機関はその違法所得を没収する以外に、5万元以下の罰金を科すことができる。
筆者の見解:
本条は初めて「行政虚開」を明確に規定した。しかし、本条の表現はさらに明確にしなければならず、「納税者は虚開行為をしているが、行政虚開だけを構成し、司法機関に移送して刑事責任を追及する必要がない場合、税務機関は不法所得を没収して罰金を科すことができる」ことを明確にしなければならない。
十七、他人の税収違法行為の実施に明確に協力した場合、処罰を受けるべき
条項:『意見聴取稿』第84本は納税者、源泉徴収義務者に銀行口座、領収書、証明書及びその他の便宜を不法に提供し、或いは納税者を教唆、誘導、援助し、源泉徴収義務者が税収違法行為を実施し、未納、過少納税又は国家輸出還付金をだまし取った場合、税務機関はその違法所得を没収する以外に、未納、過少納付又はだまし取った税金の1倍以下の罰金を処することができる。
筆者の見解:
本条では、他人の脱税に協力するには行政責任を問われるべきだと初めて規定している。しかし、本条の「その他の便宜」は実務における拡大解釈をもたらしやすく、紛争を引き起こし、行政相対人の権益を損なう可能性がある。したがって、本条の「その他の便宜」に対して明確な順方向列挙を行うことを提案する。
十八、納税前置手続を、再議前から、訴訟前に変更する
条目:『意見聴取稿』第101条第1項は納税者、源泉徴収義務者、納税保証人と税務機関との納税上の紛争が発生した場合、法に基づいて行政再議を申請することができる、行政再議決定に不服がある場合は、まず税務機関の決定に基づいて税金及び税金の遅納金を納付または解納するか、または相応の保証を提供しなければならず、それから法に基づいて人民法院に起訴することができ、人民法院は税務機関が発行した納税証明書または保証証明書に基づいて受理しなければならない。
筆者の見解:
実務の中で、現行の「徴収管理法」第88条、「税務行政再議規則」第33条の規定に基づき、納税者は税金を先に納付したり、納税保証を提供したりすることができないため、救済ルートを失った。本条は「納税前置」を再議後、訴訟前に置くことで、納税者の救済ルートを広げることができる。しかし、納税者の合法的権益をよりよく保護し、その救済ルートを確立するためには、正式に「納税前置」手続きを取り消すべきだと筆者は考えている。
19、税務サービス機構に対する監督管理を強化する
条項:『意見聴取稿』第百二条第二項国は税金関連専門サービス機構が法に基づいて税務代理業務を展開することを奨励し、税務機関は税金関連専門サービス機構と個人が税金関連専門サービスに従事する監督管理を強化しなければならない。
筆者の見解:
税務機関は「個人が税金関連専門サービスに従事するための監督管理」の内容を強化するのは広すぎて、操作性がない。筆者は現行の法律の規定に基づいて、税務機関は関連法律に限られた範囲内で税金関連専門サービス機構を監督管理すればよいと考えている。
小結
今回の改正は税務執行のレベルを強化し、納税者のコンプライアンスを高めるのに大いに役立つ。上記の筆者が注目している条項のほか、今回の「意見聴取稿」にはいくつかの改正が行われ、現行の税収徴収管理法より16条、4条削除、69条が新たに追加された。読者が今回の「意見聴取稿」に注目して検討することを歓迎し、読者の友人が4月27日までに関係機関に有益な改正提案を提出し、我が国の税収法治建設のプロセスを共同で推進することを提案することを提案する。